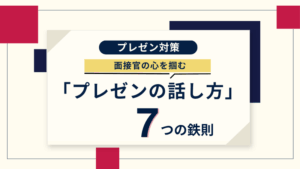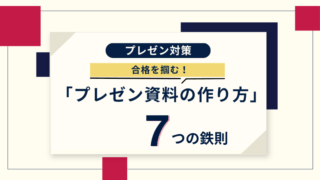
- 1. 【総合型選抜】合格を掴む「プレゼン資料」の作り方とは?専門塾が教える7つの鉄則
- 1.1. なぜ「資料」が合否を分けるのか?
- 1.2. 面接官の心を掴む「プレゼン資料」7つの鉄則
- 1.2.1. 鉄則1:「1スライド=1メッセージ」の原則
- 1.2.2. 鉄則2:文字は「書く」な、「置く」
- 1.2.3. 鉄則3:フォントは「大きく」「読みやすく」
- 1.2.4. 鉄則4:使う「色」は3色まで
- 1.2.5. 鉄則5:グラフや図解を積極的に使う
- 1.2.6. 鉄則6:完璧な「表紙」と「目次」を用意する
- 1.2.7. 鉄則7:最後は「結論」と「展望」で締める
- 1.3. KOSSUN教育ラボからのメッセージ
【総合型選抜】合格を掴む「プレゼン資料」の作り方とは?専門塾が教える7つの鉄則
こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
「プレゼン本番。何を話すかは決まったけど、スライド(資料)がうまく作れない…」 「文字だらけになって、何が言いたいか分からなくなってしまう…」
総合型選抜(AO入試)の二次選考で課されることの多い「プレゼンテーション」。 あなたの素晴らしい研究内容や独創的なアイデアを面接官(大学の教授)に伝えるため、スライドや模造紙といった「資料」は、あなたの「第2の言葉」とも言える非常に重要な武器です。
どんなに素晴らしい内容も、資料が分かりにくければ魅力は半減してしまいます。
この記事では、面接官の心を掴み、「この学生は論理的だ」と思わせる「伝わるプレゼン資料」の作り方について、その鉄則を専門塾の視点から徹底的に解説します。
なぜ「資料」が合否を分けるのか?
大学の教授陣は、プレゼン資料を通じて、あなたの「発表内容」と同時に、以下の点を見ています。
- 論理的思考力: 伝えたいことが、分かりやすい順番(構成)で並べられているか。
- 情報整理能力: 膨大な情報を、一目で理解できるように要約・図解できているか。
- 熱意と本気度: 資料の丁寧さや、聞き手に「伝えよう」とする工夫(デザイン)があるか。
つまり、資料の分かりやすさ = あなたの思考の明瞭さ として評価されるのです。
面接官の心を掴む「プレゼン資料」7つの鉄則
鉄則1:「1スライド=1メッセージ」の原則
これが最も重要です。1枚のスライドにあれもこれも情報を詰め込むのは、一番やってはいけない失敗です。
- (NG例) 1枚のスライドに「研究背景」と「研究目的」と「研究方法」をすべて書く。
- (OK例) 「研究背景」で1枚、「研究目的」で1枚、「研究方法」で1枚、とスライドを分ける。
聞き手は、あなたが話している間、そのスライドしか見られません。「このスライドで、一番伝えたいことは何か?」を常に自問自答し、メッセージを一つに絞り込みましょう。
鉄則2:文字は「書く」な、「置く」
スライドは「原稿」ではありません。あなたの話の「補助」です。
- (NG例) スライドに、話す予定の原稿をすべて書き込む。
- (OK例) キーワードや短いセンテンス(体言止めなど)だけを、箇条書きで「置く」。
文字が多すぎると、聞き手は「読む」ことに必死になり、あなたの「話」を聞いてくれなくなります。詳細は口頭で説明し、スライドはあくまで「見出し」と「キーワード」に徹しましょう。
鉄則3:フォントは「大きく」「読みやすく」
小さな文字は、それだけで読む気を失わせます。
- フォントサイズ: 最低でも24ポイント以上を推奨します。タイトルはさらに大きく。
- フォントの種類: 奇抜なフォントは避け、「ゴシック体」(例:游ゴシック、メイリオ、ヒラギノ角ゴ)を使いましょう。視認性が高く、力強い印象を与えます。明朝体は学術的な印象を与えますが、細い線がスクリーンでは見えにくいことがあるので注意が必要です。
鉄則4:使う「色」は3色まで
カラフルなスライドは、一見楽しそうに見えますが、実際は「ごちゃごちゃして見にくい」だけです。学術的なプレゼンでは、色の使い方はシンプル・イズ・ベスト。
- ベースカラー(70%): スライドの背景色(例:白)
- メインカラー(25%): 基本の文字や図の色(例:黒、濃いグレー)
- アクセントカラー(5%): 「ここだけは絶対に見てほしい!」というキーワードやグラフの一部にだけ使う強調色(例:赤、青)
この3色ルールを守るだけで、資料は驚くほど洗練され、プロフェッショナルな印象になります。
鉄則5:グラフや図解を積極的に使う
「百聞は一見に如かず」。文字でダラダラと説明するよりも、一つの図やグラフの方が、遥かに多くの情報を直感的に伝えられます。
- (NG例) 「Aは50%、Bは30%、Cは20%です」と文章で書く。
- (OK例) 上記の内容を、円グラフで示す。
複雑な関係性を示すときは「相関図」を、時系列の変化を示すときは「折れ線グラフ」を、といった具合に、情報に最適なビジュアルを選びましょう。
鉄則6:完璧な「表紙」と「目次」を用意する
プレゼンの第一印象は「表紙」で決まります。
- 表紙に入れるべき要素:
- プレゼンテーションのタイトル(あなたの研究テーマ)
- 氏名
- 所属(〇〇高等学校)
そして、表紙の次には必ず「目次(アジェンダ)」のスライドを入れましょう。 「本日は、この順番でお話しします」と最初に示すことで、面接官は話の全体像を把握でき、安心してあなたの話についてくることができます。
鉄則7:最後は「結論」と「展望」で締める
プレゼンの最後は、「ご清聴ありがとうございました」だけで終わらせてはいけません。
- 最後のスライドに入れるべき要素:
- 結論のまとめ: 「本研究の結論は、〇〇です」
- 大学での展望: 「この研究成果を土台に、貴学の〇〇学部で△△という研究へと発展させたいと考えています」
あなたの「熱意」と「将来性」を最後にもう一度強く印象付けて、プレゼンを締めくくりましょう。
KOSSUN教育ラボからのメッセージ
分かりやすい資料は、面接官のためだけにあるのではありません。「これだけ分かりやすい資料を作ったんだ」という事実が、本番でのあなたの「自信」に直結します。
今回ご紹介した7つの鉄則を使い、あなたの研究内容が120%伝わる最高の資料を作り上げてください。
もし、資料の構成やデザインに悩んだら、いつでも私たちKOSSUN教育ラボにご相談ください。あなたの挑戦を、心から応援しています。
KOSSUN教育ラボでは、総合型選抜・学校推薦型選抜(AO入試・推薦入試)に特化した対策を行っています。
受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。難関大学を中心に、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。