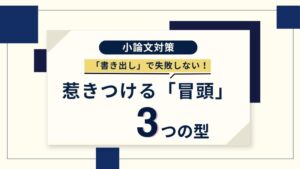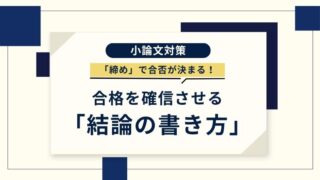
【総合型選抜】小論文の「締め」で合否が決まる!面接官に「合格」を確信させる結論の書き方
こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
「本論までは書けたけど、どうやって締めくくればいいか分からない…」 「『〜が大切だと思った』みたいな、感想文で終わってしまう…」
総合型選抜(AO入試)の小論文で、「書き出し」と同じくらい、あるいはそれ以上に受験生が悩むのが「結論(締め)」です。
小論文の「締め」は、採点者(大学の教授)が最後に読む、あなたの「最終印象」を決定づける超重要パート。ここで力尽きてしまうと、どれほど本論が素晴らしくても、あなたの論証は「未完成」という評価を受けてしまいます。
この記事では、あなたの小論文を「見事な合格答案」へと昇華させる、論理的で力強い「結論」の書き方について、その「型」と「NG例」を徹底的に解説します。
なぜ「締め」があなたの評価を左右するのか?
採点者は、あなたの「結論」を読んで、以下の2点を確認しています。
- 論理の一貫性: 「序論」で提起した問題意識や主張と、「結論」がきちんと対応しているか。話が途中でズレていないか。
- 論証の完結: 「本論」で展開した議論全体を、説得力を持ってまとめ上げ、自分の主張を再度、力強く念押しできているか。
「締め」が弱い答案は、「結局、何が言いたかったの?」という疑問を採点者に抱かせ、高得点には決して結びつきません。「締め」とは、あなたの思考が完結したことを証明する「ゴールテープ」なのです。
今すぐ使える!「締め(結論)」2つの黄金パターン
結論部分(最後の1段落)は、全体の10%〜15%程度の文字量(800字なら100字前後)で、以下の「型」に沿って書くのが鉄則です。
型1:【王道・再確認型】(最も安全で強力な型)
序論で述べた「主張」を、本論での議論を踏まえて、もう一度力強く「再確認」する書き方です。
- 構造: ①(本論の)要約 → ②(序論の)主張の再提示
- 書き出しの例: 「以上の理由から、」「このように、」「以上の考察から、」
- 【例文】(テーマ:AIと教育)
(序論の主張が「AIは教育の質を高める」だった場合)
(結論)「(①本論の要約)このように、AIは個別の学習進捗に合わせた教材の提供や、教員の雑務を軽減することを可能にする。(②主張の再提示)AIは人間の教師に取って代わるものではなく、むしろ教師がより創造的な教育活動に専念するための強力なパートナーである。以上の理由から、私は、AIを教育現場に積極的に導入することは、教育の質そのものを高めることに繋がると確信する。」
型2:【提言・展望型】(社会問題系で差がつく型)
本論での議論をベースに、一歩進んで「未来への展望」や「具体的な提言」で締めくくる、より能動的な書き方です。
- 構造: ①(本論の)要約 → ②現状の課題の再確認 → ③未来への展望・提言
- 書き出しの例: 「確かに、〜という課題は残る。しかし、」「〜という視点が、今後ますます重要になるだろう」
- 【例文】(テーマ:食品ロス問題)
(序論の主張が「食品ロスは社会全体で取り組むべきだ」だった場合)
(結論)「(①・②要約と課題)これまで見てきたように、食品ロスは倫理的な問題であると同時に、深刻な経済的損失でもある。(③提言・展望)個々の意識改革はもちろん重要だが、それだけでは限界がある。今、求められているのは、売れ残り食品を自動的にフードバンクにマッチングさせるシステムを、行政と民間企業が連携して構築することではないだろうか。技術と制度の両輪で、この問題の根本的解決を目指すべきである。」
絶対NG!評価を下げてしまう「締めの4大失敗」
NG①:新しい論点を持ち出す
最悪の失敗です。「本論で書き忘れた!」と焦って、結論部分で全く新しい議論(例:突然、海外の事例を持ち出すなど)を始めてはいけません。論理が崩壊します。
NG②:急に「感想文」になる
「〜が大切だと思った。」 「〜を学んだ。」 「〜していきたいと思う。」 小論文は「だ・である調」が基本です。急に「〜と思いました」という主観的な感想で締めると、それまでの論理性がすべて台無しになります。
NG③:序論と「矛盾」する
序論で「AIは規制すべきだ」と書いたのに、本論でメリットを書き連ねた結果、結論で「AIは活用すべきだ」と変わってしまうケース。これは「論理破綻」です。序論の主張と結論は、必ず一致させましょう。
NG④:時間切れで、結論がない
「本論の途中で答案が終わっている」のは、0点を覚悟するべき致命的なミスです。「時間内に書き上げる能力」も、小論文の採点対象です。
KOSSUN教育ラボからのメッセージ
小論文の「締め」で迷うのは、「何を書くか(=構成)」が決まっていないのに、いきなり書き終えようとするからです。
対策はただ一つ。 書き始める前に、必ず「構成メモ」を作ること。
「序論」「本論」そして「結論で何を書くか」までを、キーワードで書き出しておく。 あとは、その「設計図」に従って、清書の時間で「型」に当てはめていくだけです。
「締め」の一文で、あなたの評価は「A」にも「C」にもなり得ます。 力強い結論で、面接官にあなたの論理的思考力を強く印象付けましょう。
KOSSUN教育ラボでは、総合型選抜・学校推薦型選抜(AO入試・推薦入試)に特化した対策を行っています。
受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。難関大学を中心に、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。