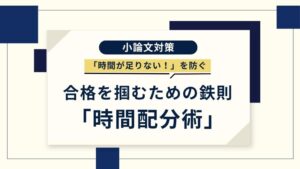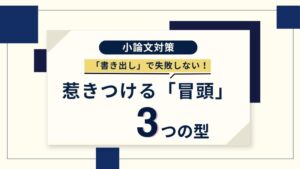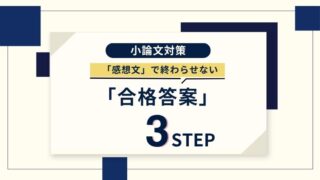
【総合型選抜】小論文の書き方ガイド決定版!「感想文」で終わらせない合格答案の3ステップ
こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
「小論文って、何を書けばいいか全然わからない…」 「いつも、ただの感想文みたいになってしまう…」
総合型選抜(AO入試)の対策で、多くの受験生が最初にぶつかる大きな壁、それが「小論文」です。
国語の作文とは異なり、小論文には明確な「ルール」と「型」が存在します。
この「型」を知らないまま書き始めてしまうと、どれだけ熱意があっても「論理的思考力がない」と判断され、評価されません。
この記事では、あなたの「書きたいこと」を合格答案に変える、小論文の「基本の型」と「書き方の3ステップ」を、専門塾の視点から徹底的に解説します。
なぜ大学は「小論文」を課すのか?
まず、敵を知るところから始めましょう。大学が小論文で知りたいのは、あなたの「文章力」だけではありません。以下の3つの力を見極めようとしています。
- 論理的思考力: 筋道を立てて、自分の主張を分かりやすく説明できるか。
- 多角的な視点: 一つの意見に固執せず、物事を様々な角度から見られるか。
- 課題発見・解決能力: 与えられたテーマ(社会問題など)の本質を理解し、自分なりの考え(解決策)を提案できるか。
これらはすべて、大学での研究やレポート作成に不可欠な能力です。小論文は、あなたが「大学で知的な探究を行う準備ができているか」を試す試験なのです。
合格答案の共通点!小論文の「基本の型」を知ろう
小論文は、基本的に「序論」「本論」「結論」の3部構成で書かれます。これが、あなたの考えを最も論理的に伝えるための「型」です。
- 序論(Introduction):
- 役割: これから何を論じるのかを宣言する(問題提起)。
- (例:「確かに〜という意見もある。しかし、私は〜と考える。」)
- 本論(Body):
- 役割: 自分の主張がなぜ正しいのかを「根拠」や「具体例」を用いて説明する(論証)。小論文の核となる部分です。
- (例:「なぜなら、第一に〜だからだ。具体的には…。第二に〜だからだ。」)
- 結論(Conclusion):
- 役割: 本論の内容をまとめ、自分の主張を再度、力強く念押しする。
- (例:「以上の理由から、私は〜と改めて主張する。」)
「感想文」が「思ったこと」を自由に書くのに対し、「小論文」は「主張(結論)」と「根拠(理由)」をセットにして、この「型」に当てはめる論理のゲームなのです。
【3ステップで完成】小論文の具体的な書き方
時間がなくても、この3ステップを踏めば、必ず論理的な文章が書けます。
STEP 1:いきなり書くな!「構成メモ」を作る(試験時間の50%)
これが合否を分けます。いきなり解答用紙に書き始めるのは、設計図なしに家を建てるようなもの。必ず問題用紙の余白に「設計図(構成メモ)」を作りましょう。
- 設問の分析: 何が問われているか?(「要約せよ」「あなたの考えを述べよ」など)
- (課題文がある場合)筆者の主張と根拠を抜き出す。
- 自分の「主張(結論)」を一言で決める。
- (例:「AIは規制すべきだ」「いや、積極的に活用すべきだ」)
- その主張を支える「根拠(理由)」を2〜3個、キーワードで書き出す。
- (例:根拠①「雇用の問題」、根拠②「教育への活用」、根拠③「反対意見への反論」)
- 「序論・本論・結論」の型に、3と4を当てはめる。
STEP 2:「型」に従って、ひたすら書く(試験時間の40%)
STEP 1で作った「構成メモ」という設計図に従って、文章(清書)を書いていきます。
- ポイント①:「だ・である調」で統一する。 「〜です。」「〜ます。」調は、感想文と見なされるのでNGです。
- ポイント②:「なぜなら〜だからだ」を徹底する。 「私は〇〇だと思う」という「意見」を書いたら、必ず「なぜなら〇〇だからだ」という「根拠」をセットで書きましょう。これが小論文の基本です。
- ポイント③:具体例や客観的な事実(データなど)を入れる。 根拠があなたの「思い込み」でないことを証明するために、具体的な例やニュース、統計などを入れると、説得力が飛躍的に上がります。
STEP 3:必ず「見直し」をする(試験時間の10%)
書きっぱなしは絶対にダメです。
- 誤字・脱字: どんなに良い内容でも、誤字脱字が多いと「注意散漫な学生」と見られ、致命的な減点対象になります。
- 主語・述語のねじれ: 文章が長くなると起こりがちです。「〜が、…である。」の繋がりは正しいかチェックしましょう。
- 序論と結論の矛盾: 最初に「賛成だ」と書いたのに、結論で「反対」になっていませんか?主張の一貫性を確認しましょう。
KOSSUN教育ラボからのメッセージ
小論文は、生まれ持った文才で書くものではありません。正しい「型」を学び、主張と根拠を論理的に組み立てる「技術」を訓練すれば、誰でも必ず書けるようになります。
今回ご紹介した3ステップを参考に、まずは短い文章からでもいいので、「型」を意識して書く練習を始めてみてください。
もし、自分一人では思考の整理が難しい、書いた答案を客観的に評価してほしいと感じたら、いつでも私たちKOSSUN教育ラボにご相談ください。あなたの挑戦を、心から応援しています。
KOSSUN教育ラボでは、総合型選抜・学校推薦型選抜(AO入試・推薦入試)に特化した対策を行っています。
受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。難関大学を中心に、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。