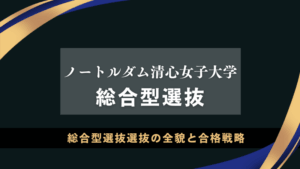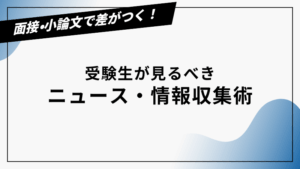【総合型選抜のキホン】文部科学省が示すAO・推薦入試の「ルール」とは?
こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
「総合型選抜(AO入試)って、大学が自由にやっているの?」 「国(文部科学省)は、この入試についてどう考えているんだろう?」
近年、大学入試の多様化が進む中で、総合型選抜や学校推薦型選抜の重要性はますます高まっています。これらの入試制度の大きな方向性を定め、各大学にガイドラインを示しているのが文部科学省です。
この記事では、総合型選抜を理解する上で欠かせない、文部科学省の役割と、受験生が知っておくべき制度のポイントについて、専門塾の視点から分かりやすく解説します。
総合型選抜とは?文部科学省の定義
文部科学省は、総合型選抜を以下のように位置づけています。
詳細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせることによって、入学志願者の能力・適性や学習に対する意欲、目的意識等を多面的・総合的に評価・判定する入試方法。 (※従来の「AO入試」は2021年度入試から「総合型選抜」へと名称変更されました)
ポイントは、「多面的・総合的」という点です。学力試験だけでは測れない、受験生一人ひとりの個性や経験、将来への可能性を、時間をかけて丁寧に見極めようというのが、国が示す総合型選抜の基本的な考え方です。
なぜ文部科学省は総合型選抜を推進するのか?
文部科学省が総合型選抜を推進する背景には、「学力の3要素」を多面的に評価し、高校教育と大学教育をスムーズに接続させたいという狙いがあります。
【学力の3要素】
- 知識・技能
- 思考力・判断力・表現力
- 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
従来の学力試験(一般選抜)では、主に「知識・技能」が評価の中心でした。しかし、これからの社会で活躍するためには、「思考力・判断力・表現力」や「主体性・協働性」といった能力がますます重要になります。
総合型選抜は、まさにこれらの能力を評価するのに適した入試方式として期待されているのです。特に、高校での探究活動などを通じて培われる主体性や思考力を、大学入試で適切に評価しようという意図があります。
受験生が知っておくべき「文科省ルール」のポイント
文部科学省は、総合型選抜の実施にあたり、各大学に対して一定のガイドラインを示しています。受験生として特に知っておきたいポイントは以下の通りです。
- 評価方法の明確化: 各大学は、**アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)**を明確にし、どのような能力や資質を評価するのかを具体的に示す必要があります。受験生は、志望大学のアドミッション・ポリシーを熟読することが対策の第一歩です。
- 学力評価の必須化: 名称がAO入試から総合型選抜に変わった際、「学力の3要素」を評価することがより強く求められるようになりました。具体的には、**「小論文、プレゼンテーション、口頭試問、実技、各教科・科目に係るテスト、資格・検定試験の成績、大学入学共通テストのうち少なくともいずれか一つを活用する」**ことが必須とされています。つまり、単なる書類審査や面接だけでなく、何らかの形で学力や思考力が評価されるということです。
- 出願時期・合格発表時期: 総合型選抜の出願時期は原則として9月1日以降、合格発表は11月1日以降と定められています(一部例外あり)。これにより、受験生が高等学校での学習活動に十分に取り組む時間を確保することが意図されています。
KOSSUN教育ラボからのメッセージ
総合型選抜は、文部科学省が示す大きな方向性のもと、各大学が工夫を凝らして実施している入試制度です。
国の示す「学力の3要素」や評価方法のルールを理解した上で、志望大学のアドミッション・ポリシーや具体的な選考方法を深く研究することが、合格への最短距離となります。
もし、制度が複雑でよく分からない、自分に合った大学・学部選びに悩んでいると感じたら、いつでも私たちKOSSUN教育ラボにご相談ください。あなたの挑戦を、心から応援しています。
KOSSUN教育ラボでは、総合型選抜・学校推薦型選抜(AO入試・推薦入試)に特化した対策を行っています。
受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。難関大学を中心に、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。