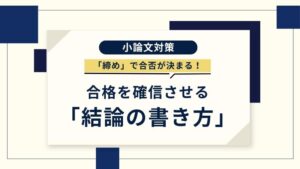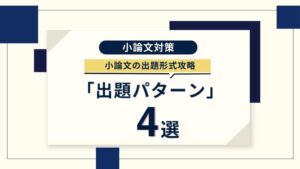【総合型選抜】その小論文、採点者に読まれてないかも?減点されない「文章術」7選
こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
「主張も根拠も書いたはずなのに、なぜか評価が低い…」 「文章が幼稚だと言われてしまう…」
総合型選抜(AO入試)の小論文で、「何を(WHAT)書くか」(=構成力、論理性)と同じくらい重要なのが、「どのように(HOW)書くか」(=文章術)です。
どれほど素晴らしいアイデアも、読みにくい稚拙な文章で書かれていれば、その価値は半減してしまいます。大学の教授である採点者は、あなたの文章から「知性」や「論理的思考力」を読み取っています。
この記事では、「感想文」を卒業し、「知的な合格答案」として読んでもらうための、減点されない文章術を7つに厳選して解説します。
なぜ「文章術」が合否を分けるのか?
小論文は、あなたと採点者との「文字を通じたコミュニケーション」です。読みにくい文章、失礼な文章は、それだけで「他者への配慮が欠けている」「知的な訓練を積んでいない」というマイナス評価に繋がります。
逆に、読みやすくクリアな文章は、「思考が明晰である」という強力なアピールになります。難しい言葉を使う必要はありません。「シンプルで、正確に伝わること」こそが、小論文における最高の文章術です。
1. 文末は「だ・である調」で統一する
【最重要の基本ルール】
- (NG例)「〜だと考える。なぜなら、〜が大切だからです。」
- (OK例)「〜であると考える。なぜなら、〜が大切だからだ。」
「です・ます調」は、感想文やエッセイの文体です。小論文は、客観的な論証を行う「論文」の仲間。「だ・である調」または「である・と考える」調で統一するのが絶対のルールです。これが守れていない答案は、その時点で読むのをやめられる可能性すらあります。
2. 「一文」は短く、「主語」と「述語」を近づける
読みにくい文章の最大の原因は、「一文が長すぎること」です。
- (NG例)「近年、スマートフォンの普及によって、若者の活字離れが深刻な問題となっているが、これは単に若者だけの問題ではなく、魅力的なコンテンツを提供できない社会全体の課題であると私は考える。」
- →(「〜が、〜で、〜と考える」と続き、主語「これは」と述語「考える」が離れすぎている)
- (OK例)「近年、スマートフォンの普及により、若者の活字離れが深刻化している。しかし、これは若者だけの問題ではない。むしろ、魅力的なコンテンツを提供できない社会全体の課題である。(ピリオド「。」で区切る)」
一文の目安は60文字程度。「〜が、」「〜ので、」で無限に繋げるクセをやめ、「。」を打つ勇気を持ちましょう。
3. 「〜と思う」を封印し、「〜と考える」と断言する
- (NG例)「私は、〇〇が必要だと思う。」
- (OK例)「私は、〇〇が必要であると考える。」「〇〇が必要である。」「〇〇が必要であろう。」
「〜と思う」は、あなたの主観的な「感想」と受け取られます。小論文は、あなたの「感想」ではなく「主張」を述べる場です。「〜と考える」「〜である」と断言することで、文章に「論」としての強さと責任感が生まれます。
4. 「こそあど言葉」と「接続詞」を多用しない
「これは」「それは」「あのような」といった指示語(こそあど言葉)は、文章を曖昧にします。
- (NG例)「筆者はAだと主張する。しかし、それは違うと考える。」
- (OK例)「筆者はAだと主張する。しかし、その意見には賛同できない。」
また、「しかし、」「そして、」「だから、」といった接続詞も、使いすぎると文章のリズムが悪くなり、幼稚な印象を与えます。本当にその接続詞が必要か、一度立ち止まって考えましょう。
5. 「〜ということ」と「〜というもの」を削除する
これらは、文章を回りくどくする「贅肉」です。意識的に削除しましょう。
- (NG例)「AIの発展は、人間の仕事を奪うというものである。」
- (OK例)「AIの発展は、人間の仕事を奪う。」
- (NG例)「大切なのは、諦めないということだ。」
- (OK例)「大切なのは、諦めないことだ。」
この「贅肉」を削ぎ落とすだけで、文章は一気に引き締まります。
6. 「ら抜き言葉」や「話し言葉」を徹底的に排除する
「見れる(見られる)」「食べれる(食べられる)」といった「ら抜き言葉」は、教養を疑われる致命的な文法ミスです。
また、「すごい」「めっちゃ」「〜みたいな」「ちゃんと」といった「話し言葉」も、小論文では絶対にNGです。
- すごい → 非常に、著しく
- ちゃんと → 適切に、確実に
常に「書き言葉」としての品格を意識してください。
7. 誤字・脱字は「0点」の覚悟でチェックする
どれほど論理的な文章でも、誤字・脱字が多ければ、「注意散漫な学生」「物事を雑に扱う人物」という最悪のレッテルを貼られます。
特に、「体験」と「体現」、「保障」と「保証」、「追求」と「追及」など、同音異義語の変換ミスは頻発します。
試験時間の最後の5分〜10分は、必ず「見直し」の時間にあて、誤字・脱字をゼロにする努力をしましょう。
KOSSUN教育ラボからのメッセージ
小論文は、あなたの「思考」を採点者に届けるためのコミュニケーションです。あなたの素晴らしい思考も、稚拙な「文章」という器に入れてしまっては、こぼれ落ちて伝わりません。
今回ご紹介した7つの文章術は、すぐに実践できるテクニックでありながら、あなたの答案の「知性」を格段に引き上げるものです。
日頃から「型」を意識し、「伝わる」文章を書く訓練を積んでいきましょう。
KOSSUN教育ラボでは、総合型選抜・学校推薦型選抜(AO入試・推薦入試)に特化した対策を行っています。
受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。難関大学を中心に、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。