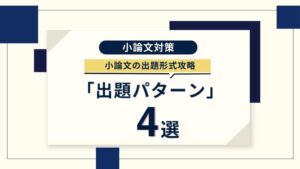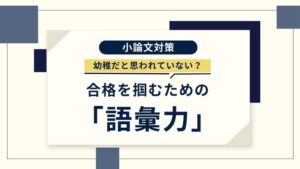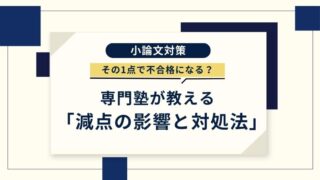
- 1. 【総合型選抜】小論文で「漢字が書けない!」その1点で不合格になる?専門塾が教える減点の影響と対処法
- 2. 結論:「漢字1字」で不合格にはならない。ただし…
- 3. 漢字を忘れた瞬間に「やってはいけない」3つのNG行動
- 3.1. NG①:パニックになり、フリーズする(最悪の選択)
- 3.2. NG②:間違った漢字を、自信満々に書く(誤字)
- 3.3. NG③:創作漢字を作る
- 4. 忘れた瞬間の「正しい対処法」ベスト3
- 4.1. 対処法①:【最優先】別の言葉に「言い換える」(パラフレーズ)
- 4.2. 対処法②:【次善策】ひらがなで書く
- 4.3. 対処法③:【最終手段】その言葉を使わずに文を構成し直す
- 5. 日頃からできる「漢字忘れ」予防策
- 5.1. KOSSUN教育ラボからのメッセージ
【総合型選抜】小論文で「漢字が書けない!」その1点で不合格になる?専門塾が教える減点の影響と対処法
こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
「小論文の試験本番、『推薦』の『薦』ってどう書くんだっけ…?」 「『環境』の『環』が思い出せない!どうしよう!」
試験本番、アドレナリンが出ている中で、普段なら書けるはずの漢字が急に思い出せなくなり、頭が真っ白に… これは、総合型選抜(AO入試)の小論文を受験する多くの学生が経験する、非常に恐ろしい「あるある」です。
「たった1つの漢字ミスのせいで、不合格になったらどうしよう…」
この記事では、その不安に答えます。小論文で漢字を忘れた場合、合否にどれだけ影響するのか、そしてその場でどう対処すべきか、専門塾の視点から徹底的に解説します。
結論:「漢字1字」で不合格にはならない。ただし…
まず、結論から言います。 小論文試験で、漢字を1つや2つ忘れた(あるいは間違えた)こと「だけ」が理由で、不合格になることは、まずありません。
なぜなら、大学の教授である採点官が小論文で評価しているのは、あなたの「漢字力」(国語の書き取り試験)ではなく、「論理的思考力」だからです。
採点官が見ているのは、
- 主張(結論)は明確か?
- その主張を支える根拠(理由)は説得力があるか?
- 文章全体の構成(序論・本論・結論)は論理的か?
という点です。 全体の論理が完璧で、素晴らしい主張が展開されていれば、漢字の1つや2つのミスは「小さな減点」で済みます。
漢字を忘れた瞬間に「やってはいけない」3つのNG行動
ただし、漢字を忘れたこと「自体」よりも、その後の「あなたの行動」が、合否を分ける致命傷になることがあります。
NG①:パニックになり、フリーズする(最悪の選択)
一番やってはいけないことです。 「漢字が出てこない!」と焦り、その一文字に5分も10分も使ってしまう。その結果、時間が足りなくなり、結論まで書ききれなかった。 これこそが、不合格に直結する最大の失敗です。「未完成の答案」は、採点の土俵にすら上がれません。
NG②:間違った漢字を、自信満々に書く(誤字)
「忘れる」ことよりも、「間違える(誤字)」ことの方が、減点の度合いは大きい可能性があります。なぜなら、それは「知識が曖昧である」という明確な証拠になるからです。
- (例)「問題点を追求する」(正:追究)
- (例)「医療保証を充実させる」(正:保障)
自信がない漢字を無理に書くのは、非常に危険です。
NG③:創作漢字を作る
論外です。採点者への印象は最悪になります。
忘れた瞬間の「正しい対処法」ベスト3
では、本番で「書けない!」となった時、どうすればいいのか。以下の優先順位で対処してください。
対処法①:【最優先】別の言葉に「言い換える」(パラフレーズ)
これが最もスマートで、減点のリスクがゼロの「最強の対処法」です。小論文は、あなたの語彙力も見られています。
- 「推薦」が書けない → 「勧める」「推す」
- 「深刻な」が書けない → 「重大な」「大きな影響を与える」
- 「妨げる」が書けない → 「邪魔をする」「ブレーキをかける」
- 「脆弱な」が書けない → 「もろい」「弱い」
- 「グローバル化」が書けない → 「国際化」「世界の一体化」
日頃から、一つの言葉を別の言葉で説明する訓練をしておくと、本番でこの「言い換え力」が発揮できます。
対処法②:【次善策】ひらがなで書く
どうしても言い換えが思い浮かばない、あるいは「環境(かんきょう)」のような、言い換えが難しい必須キーワードだった場合。
最終手段として、「ひらがな」で書いてください。
- (例)「この問題は、私たちの生活かんきょうに直結する」
もちろん、多用すれば「漢字を知らない学生だ」と幼稚な印象を与え、減点されます。しかし、「間違った漢字を書く」「パニックで止まる」よりは、何百倍もマシな選択です。 採点官も「この受験生は、この漢字を忘れたんだな。でも、論理はしっかりしている」と判断し、議論の続きを読んでくれます。
対処法③:【最終手段】その言葉を使わずに文を構成し直す
少し高度ですが、「その言葉がなくても伝わるように、文の構造自体を変える」という方法です。
日頃からできる「漢字忘れ」予防策
- 「読む」だけでなく「書く」: スマホやPCの予測変換に頼り切っていると、人間の脳は驚くほど漢字を忘れます。小論文対策は、必ず「手書き」で行いましょう。
- 「頻出テーマ」の漢字を覚える: 小論文で問われる漢字はある程度決まっています。「環境」「医療」「情報」「格差」「持続可能」「多様性」「協働」など、頻出テーマのキーワードは、必ず手で書いて練習しておきましょう。
KOSSUN教育ラボからのメッセージ
小論文の本質は、あなたの「思考」を伝えることです。 漢字を一つ忘れても、あなたの「論理」が崩れるわけではありません。
本番で忘れても、「あ、忘れたな」と冷静に受け止め、すぐに「言い換える」か「ひらがなで書く」かに切り替え、絶対にペンを止めないこと。その「冷静な判断力」と「完遂力」こそが、総合型選抜で求められる力です。
KOSSUN教育ラボでは、総合型選抜・学校推薦型選抜(AO入試・推薦入試)に特化した対策を行っています。
受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。難関大学を中心に、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。